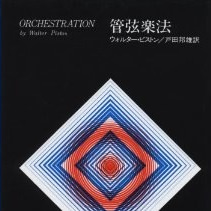管弦楽法とは、オーケストラの曲を書くための技法のことです。
編曲がうまくなるコツの一つは、楽器の事を知ることです。どんな楽器があるのか、音色、奏法、音域、得意なフレーズ、どの楽器と相性がいいのか…など。これはオーケストラ以外でも言えますね。
ウォルターピストンの管弦楽法はの2/3ほどが楽器そのものの説明になってます。近代のものまで譜例付きで説明してあるのでわかりやすいです。
ヴァイオリンならG線がどんな音でどのフレーズに合うだとか、1つ1つがかなり詳細で膨大な情報量なので、僕はトイレに置いておいて入るたびに適当なページを読んでいます。
目次
第1部 オーケストラの諸楽器
1 弦楽器
2 ヴァイオリン
3 ヴィオラ
4 チェロ
5 コントラバス
6 木管楽器
7 フルート
8 オーボエ
9 クラリネット
10 ファゴット
11 金管楽器
12 ホルン
13 トランペット
14 トロンボーン
15 テュバ
16 打楽器
17 ハープ
18 鍵盤楽器
第2部 管弦楽法の分析
19 構造の諸型 – 第1型:管弦楽のユニソン
20 構造の諸型 – 第2型:旋律と伴奏
21 構造の諸型 – 第3型:副次的旋律
22 構造の諸型 – 第4型:声部書法(パート・ライティング)
23 構造の諸型 – 第5型:対位法的構造
24 構造の諸型 – 第6型:和弦
25 構造の諸型 – 第7型:複合構造
第3部 管弦楽法の実習問題
26 旋律のオーケストレーション
27 背景と伴奏
28 和弦の総譜配置
29 声部の動かし方と対位法
第2部は実際の楽器の使い方。ここを読めば大きい編成のオーケストラのスコアも読み方が分かってきます。一つ一つのパートの意図が理解出来るようになる。アナライズを始める前に読んでおくべきですね。
特に和弦の考察はオーケストラアレンジ初心者には嬉しいです。しかし譜例が少ないので実際のスコアをアナライズして好きな重ね方を勉強したほうがよさげです。
あと、この本の前に和声法を習得しておくのは絶対です。和弦には音度がかなり関係してるので。対位法も出来れば、という感じです。
第3部の実習問題もいいですね。
この本を踏まえて、DTMにおいては生楽器を扱うのとは考えを変えていったほうがいいと思ってます。特に音色についてですが、サンプルの方が表情が乏しいので、それを補う工夫をしないとなあと。
そもそも表情を付けるようなソロを入れない、音色を加工する、DTMならではの音色で補うなど…僕も答えを探ってます。逆に無茶な奏法が出来るのはDTMの強みなんですけど。サンプルの質も考慮したいです。
弾いてもらう時と、打ち込みで完結する時に書き分けられるのがベストですね。